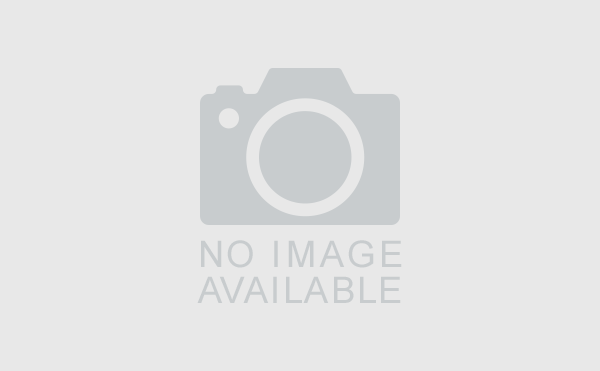スピード暗記 産業の発達と幕府政治の働き
「●●●」をクリックすると、答えが表示されます。
江戸時代には、●●●と呼ばれる貨幣が発行されました。また、幕府は五街道を整備しました。
「●●●」と呼ばれた大阪から江戸への輸送が必要になると、醤油や油を運ぶ●●●、酒を運ぶ●●●が定期的に往復しました。海路は●●●航路と●●●航路が開かれました。
このころ、●●●が多く建てられ、都市では、●●●と呼ばれる同業者組合が作られました。
第五代将軍の●●●は●●●を学ぶことを勧めました。また、●●●を出しました。
元禄文化では、●●●が●●●の台本を書き、俳諧では、●●●が新しい作風を生み出しました。●●●は浮世絵を書きました。その他には、歌舞伎も広まりました。
徳川吉宗は●●●という裁判の基準になる法律を定め、目安箱も設置しました。これらの●●●の改革によって財政は一時的に立ち直りました。
このころ、●●●工業や●●●工業などが行われました。
18世紀になると百姓は、●●●を起こし、●●●などをしました。
●●●は●●●を奨励しました。この時代には、商工業が発達しました。しかし、賄賂の横行や浅間山の噴火による凶作により、●●●は老中を辞めさせられました。
次に老中になった●●●は●●●改革を行いました。ききんに備えるために、米を蓄えさせ、朱子学以外の学問は禁止しました。
●●●は「●●●」を著し、国学を大成しました。●●●は「●●●」を出版し、●●●学の基礎を築きました。●●●は、全国の海岸線を測量し、正確な日本地図を作りました。
19世紀の初めに庶民が文化の担い手となった文化を●●●文化といいます。
●●●は美人画、●●●や●●●は風景画をつくりました。
このころ、●●●や藩校が各地に設けられました。
幕府は●●●を出しました。
●●●は奉行所の対応に不満を持ち、●●●の乱を起こしました。
老中の●●●は幕府の力を回復させるため、●●●の改革を行いました。株仲間の解散や異国船打払令の廃止などを行いましたが、改革は失敗に終わりました。